1. 戦前の複線教育
戦前の日本の教育制度は、複数の進路が並行して存在する複線教育制度であった。義務教育である尋常小学校(6年)修了後、12歳前後という早い段階で進路が分岐し、その後は原則として別の線路へ乗り換えることが困難な構造になっていた。
最下層かつ多数派は、尋常小学校卒業後にそのまま就職する層である。農業、家業、工場労働、丁稚奉公などに進み、同世代の5~6割以上を占めていた。制度上はここで教育が完結する人々であり、これが当時の社会の基盤を形成していた。
次に位置するのが実業学校系ルートである。工業学校、商業学校、農業学校、水産学校などがあり、修業年限は3~5年で、実務能力の育成を目的としていた。尋常小学校卒業者のうち15~20%前後が進学し、企業や地域社会の中核的な技術者・事務担当者となった。原則として大学進学は想定されておらず、ここでも線路は閉じていた。
この実業ルートの頂点に位置したのが、高等工業学校・高等農林学校・高等商業学校といった旧制専門学校である。入学には高い学力が要求され、実業学校卒や旧制中学校卒の優秀層が集まった。卒業生は重工業、農政、金融、官庁、商社などで活躍し、日本の近代化と産業化を実務面で支えた。同世代に占める割合は合計で約1%前後で、帝国大学とほぼ同規模であった。戦後の国立大学工学部・農学部・経済学部の母体となったのは、主としてこの層である。
学問エリートの中核をなしたのが、旧制中学校―旧制高等学校―帝国大学という文官エリートルートである。旧制中学校に進学できたのは同世代男子の7~8%程度にすぎず、さらに旧制高等学校を経て帝国大学へ進学できたのは、同世代の1%未満であった。このルートは官僚、研究者、法曹、医師など、国家運営と学問の中枢を担う人材を養成した。
これらとは完全に別系統として存在したのが、陸軍士官学校・海軍兵学校である。これらは文部省管轄の教育制度ではなく、陸軍省・海軍省が直接運営する軍事エリート養成機関であった。旧制中学校卒業相当の学力と厳格な身体検査を課し、とりわけ海軍兵学校は数学・理科において旧制高校最上位層に匹敵する難度を誇った。合格者は同世代の0.1~0.3%程度で、卒業と同時に将校として任官し、国家権力の中枢に直結する最上位レーンを形成していた。
このように戦前日本は、
①現業・労働層
②実業・技術中間層
③実務エリート(高等専門学校)
④文官エリート(帝国大学)
⑤軍事エリート(陸士・海兵)
という複数の教育・選抜ルートを並行的に運用していた。早期選別である一方、それぞれの線路内では高度に洗練された教育が行われ、社会全体としては合理的に機能していた。
戦後、この複線構造は「民主化」の名のもとに単線化され、軍学校は廃止され、専門学校は大学へ再編された。しかし、制度上は単線になった一方で、実際には学校間・学部間・大学間の序列として、複線構造は形を変えて存続しているといえる。
戦後の単線教育
戦後日本の教育制度は、戦前の複線教育体制を意図的に解体し、単線型教育制度へ転換することから始まった。この転換は自然な進化ではなく、占領政策と戦前体制への反省を背景とした、強い制度的意思にもとづく改革であった。
戦前の教育制度では、尋常小学校修了後の12歳時点で進路が分岐し、実業、学問、軍事という複数のレーンが並行して存在していた。戦後改革はまずこの早期選別を問題視し、すべての国民に共通の基礎教育を保証することを最優先目標に据えた。その結果として導入されたのが、6・3・3・4制である。小学校6年と中学校3年が義務教育となり、進路分岐の時点は15歳まで引き上げられた。
この改革により、戦前には多数派であった「小学校卒で就職」という進路は制度上消滅し、すべての子どもが中等教育前期まで同一課程を学ぶことになった。教育は選抜装置というよりも、国民統合の装置へと位置づけを変えたのである。
次に解体されたのが、戦前の実業学校体系である。工業学校・商業学校・農業学校といった中等実業教育は、高校段階に再編され、「普通科」と「職業科」という形で一つの制度に包摂された。戦前のように制度的に閉じた実業ルートは消え、形式上はどの高校からも大学進学が可能となった。これにより、進路の固定化は緩和されたが、同時に高度な職業教育の独立性は弱まった。
戦前の実務エリート養成機関であった高等工業学校・高等農林学校・高等商業学校は、戦後改革において新制大学へと格上げ・再編された。東京工業大学、一橋大学、神戸大学をはじめ、多くの国立大学の工学部・農学部・経済学部は、これら旧制専門学校を母体としている。制度上は「大学」として一本化されたが、教育内容や教員文化には戦前の実学志向が色濃く残った。
一方、戦前の学問エリートルートであった旧制高等学校は廃止され、その機能は新制大学の教養課程(のちの教養部)に吸収された。旧制高校が担っていたエリート形成機関としての役割は希薄化し、大学進学前の身分的な選別装置は制度上消滅した。これにより、帝国大学を頂点とする明確な学歴ピラミッドは、表向き解体された。
最も徹底的に否定されたのが、陸軍士官学校・海軍兵学校に代表される軍事エリート養成ルートである。これらは学校制度として完全に廃止され、戦後教育制度との連続性は意図的に断ち切られた。国家が若年層を直接選抜し、身分と権力を付与する仕組みそのものが否定され、戦後日本において「軍学校」は存在しないものとなった。
こうして戦後日本の教育制度は、制度上は**「中学校までは全員共通、高校以降は自由選択、大学は能力主義」**という単線構造に再設計された。戦前のように、教育制度そのものが社会的役割や身分を直接割り当てることはなくなったのである。
しかし、その結果として複線構造が完全に消えたわけではない。実際には、普通科高校と職業科高校、進学校と非進学校、大学間・学部間の序列といった形で、選抜と分化は非公式かつ市場的に再編された。戦前は制度として明示されていた複線が、戦後は「見えにくい複線」として再生産されることになった。
要するに、戦前教育が「国家が役割ごとに人材を配置する制度」であったのに対し、戦後教育は「形式的平等の下で競争によって分化が生じる制度」へと転換したのである。複線教育は廃止されたが、社会が必要とする分業構造そのものが消えたわけではなく、複線は制度から文化へと移行したと評価できる。
「大学生=エリート」ではなくなった瞬間、大学内部での序列化が進んだ。
- 大学名が「能力の代理指標」になった
- 入試難易度=社会的評価、という構図が成立
- 教員数
- 研究設備
- 大学院規模
- 研究費配分
これらが 旧制大学に集中していた。
教育の「中立な競争」の結果ではなく、初期条件が圧倒的にち
「能力・希少性・資源差」まで消す設計ではなかった。
そのため、教育機会が拡大するほど、 相対評価(偏差値)による新しい階層化が不可避的に発生した。
単線化=誰でも進学可能になる制度であるが平等化=全員が同じ到達点に立つ制度ではなかった。
高等教育の急拡大が「選抜」を不可避にした
戦後改革によって日本の教育制度は単線化され、制度上はすべての国民に同一の進路可能性が開かれた。しかし、この理念は長期的には別の問題を内包していた。それが、高等教育の急激な量的拡大である。
高度経済成長期以降、日本では大学・短期大学・高等専門学校が急増し、進学率は一貫して上昇した。1960年代には一割台であった大学進学率は、1990年代には三割を超え、21世紀には五割前後に達した。高等教育はもはや一部のエリートの特権ではなく、大衆教育として制度化されたのである。
しかし、高等教育が大衆化しても、社会が必要とする高度専門職や意思決定層の人数が比例して増えるわけではない。官僚、研究者、専門職、上位管理職といったポストは依然として限られており、学歴が希少性を失う一方で、地位の希少性は維持された。この不均衡が、新たな形の選抜を不可避にした。
戦前の複線教育では、選抜は制度として明示されていた。どの学校に進めば、どの社会的役割に就くのかが、あらかじめ定められていた。それに対し戦後の単線教育では、「誰でも大学へ行ける」という建前の下で、選抜は後景化され、不可視化された。しかし、選抜そのものが消滅したわけではなく、むしろ形を変えて強化された。
まず、高校段階での選抜が激化した。中学校までは共通課程であっても、高校入試によって進学校と非進学校が分化し、大学進学可能性は実質的にここで大きく制限される。これは戦前の「小学校卒での分岐」が、「中学校卒での分岐」へと後ろ倒しされたにすぎない。
次に、大学間の序列が決定的な意味を持つようになった。大学数が増え、進学率が上昇するにつれ、「大学に入るか否か」よりも、「どの大学に入るか」が社会的評価を左右するようになった。旧制時代には帝国大学が明確な頂点として存在していたが、戦後は偏差値や入試難易度による暗黙のヒエラルキーが形成された。
さらに、学部・専攻内での選抜も強まった。医学部、難関理工系、法学部など、社会的リターンの大きい分野には競争が集中し、同じ大学内でも進路の格差が拡大した。これは、戦前の「文官・技術官・軍人」という制度的分化が、学部選択という形で再出現したものとも言える。
このようにして戦後日本は、単線教育の内部に多層的な選抜構造を埋め込むことで、高等教育の大衆化と社会的分業の両立を図ることになった。表面上は平等であるが、実態としては複雑で見えにくい選抜が連続する制度へと変質したのである。
要するに、高等教育の急拡大は、選抜を不要にしたのではなく、むしろ**「どこで、どのように選抜するか」という問題を先送りし、分散させただけ**であった。戦前は制度が露骨に選抜を担っていたのに対し、戦後は教育市場と競争がその役割を代替することになった。
この結果、現代日本の教育制度は、
形式的には単線、実質的には多線という矛盾した構造を抱えることになった。高等教育の大衆化は平等化をもたらしたが、同時に選抜の不可避性をより見えにくく、かつ個人の責任として引き受けさせる仕組みを生み出したのである。
- 「選抜が“自己責任化”した結果、何が起きたか」
- 「学力ではなく“家庭背景”が効くようになった理由」
「大学生=エリート」ではなくなった瞬間、大学内部での序列化が進んだ。

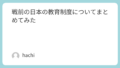

コメント